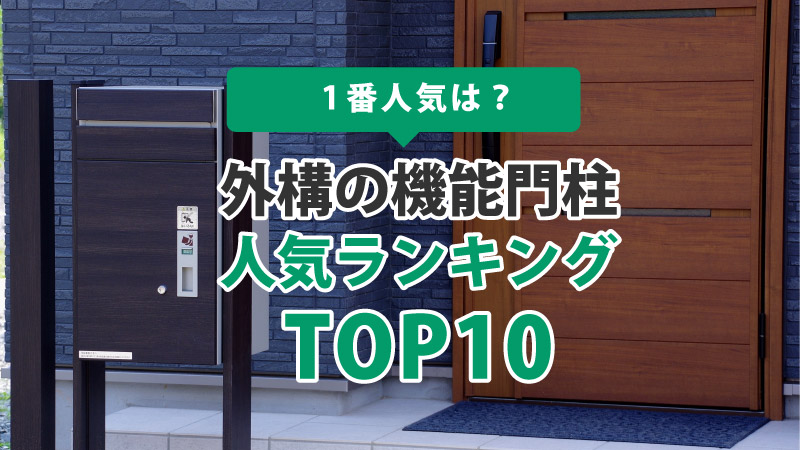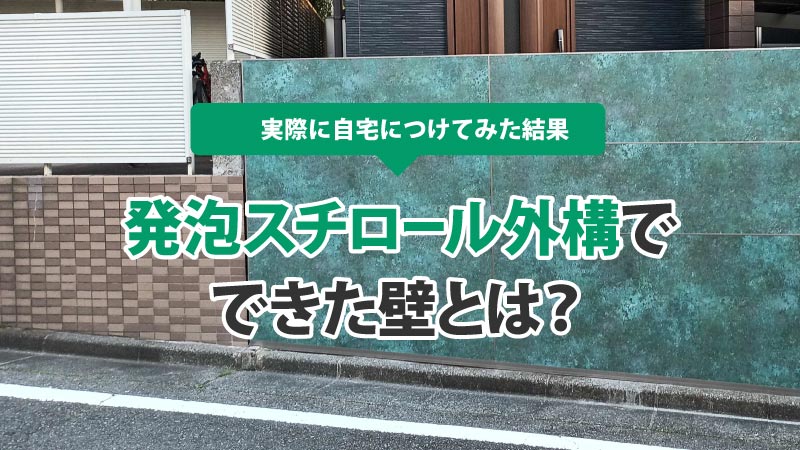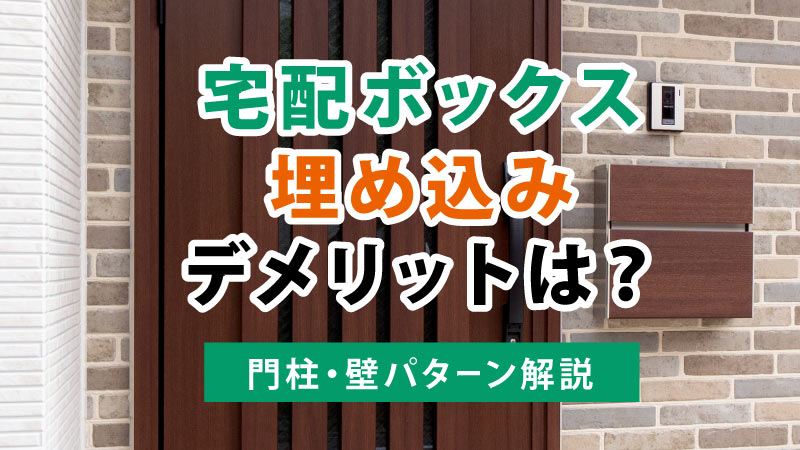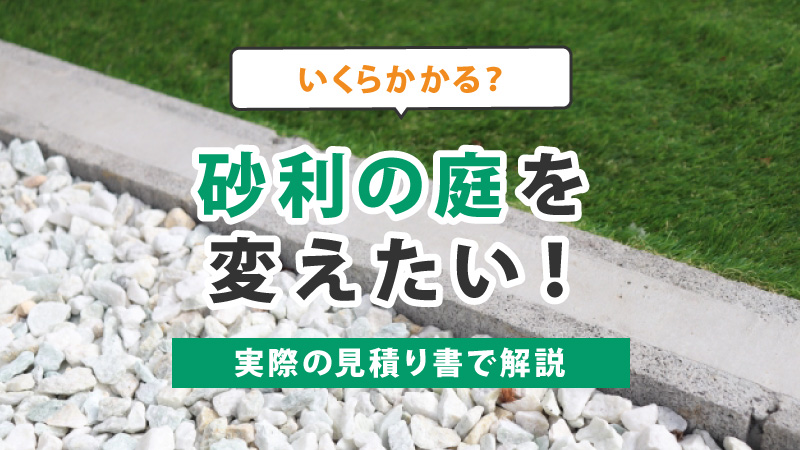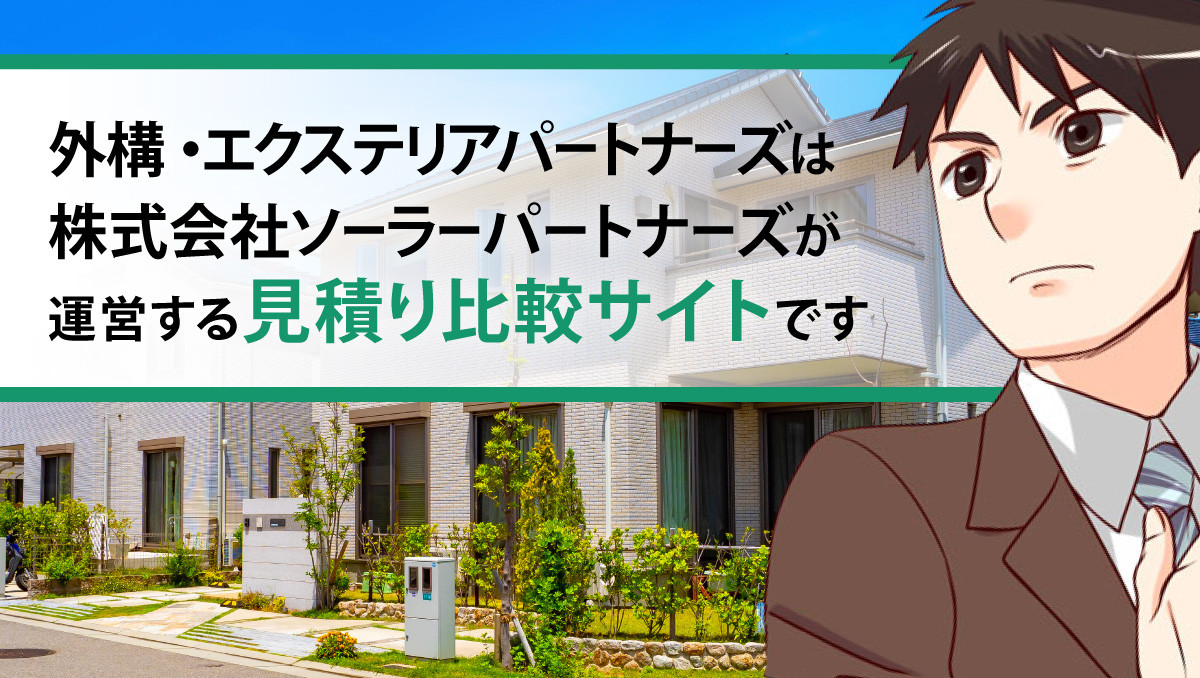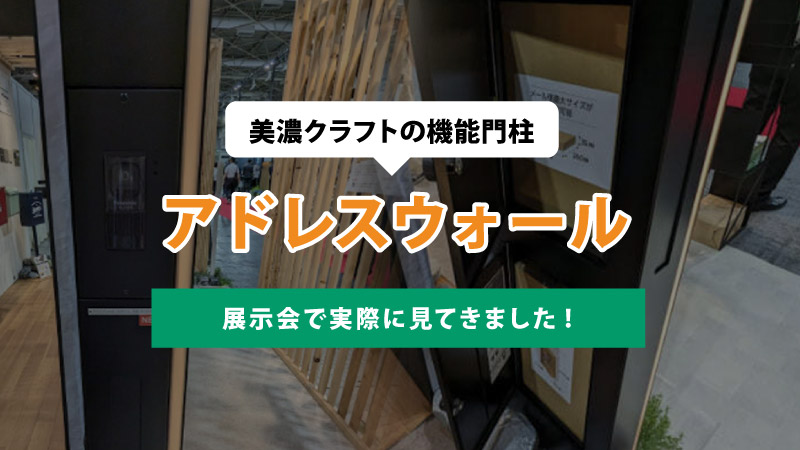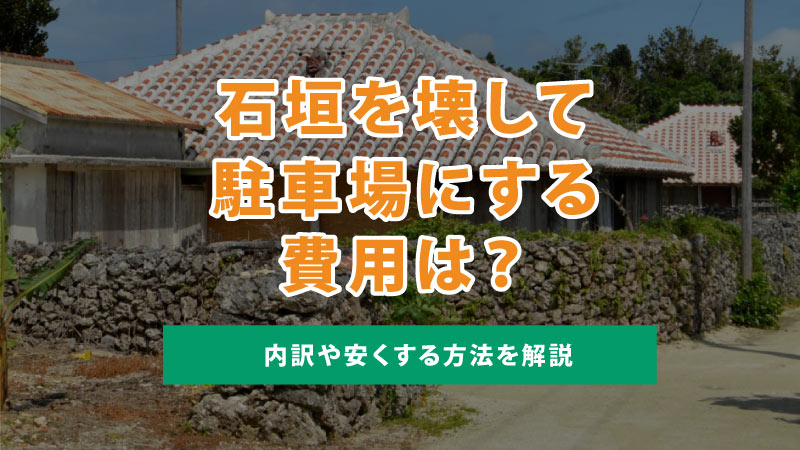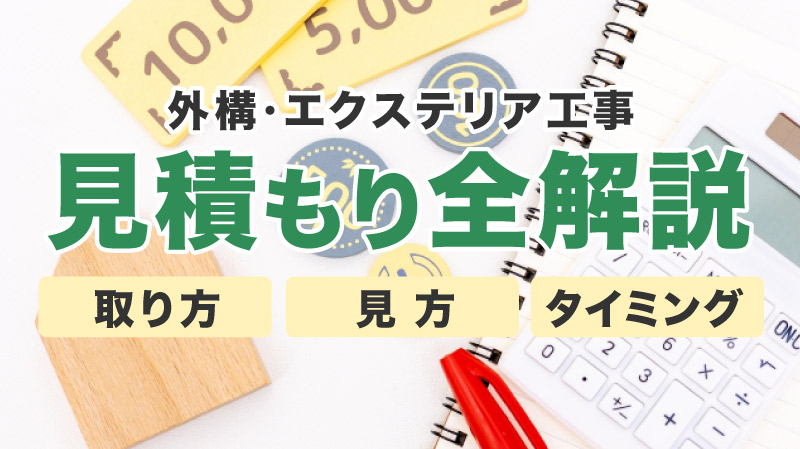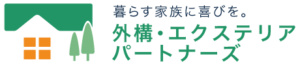“外構から暮らしを変える”という挑戦―YKK APが選ばれ続ける理由とは

エクステリアの大手3社の一つで業界で確かな存在感を放っているのがYKK AP。
「YKKって、ファスナー・窓の会社でしょ?」
そんな声がまだ根強く残る中、実はエクステリアでも確かな品質でモノづくりをしています。
その背景には、ファスナー開発で培った技術と、モノづくりへの一貫したこだわりがある。
見た目の美しさはもちろん、防犯性や施工性、さらには環境配慮まで――細部に宿る思想が、住まいに“10年先の満足”を届けています。
今回のインタビューでは、そんなYKK APの開発・製造の舞台裏から、これからの暮らしに求められる外構のあり方まで、YKK APエクステリア本部長の苅谷さんにじっくりと話を聞いてきました。

苅谷 昭斉氏
1993年 10月 YKK AP株式会社 営業企画部
2012年 4月 YKK AP株式会社 特需事業部 東京営業部長
2018年 4月 YKK AP株式会社 特需事業部 住宅営業統括部長
2019年 4月 YKK AP株式会社 特需事業部 副事業部長 兼 事業企画室長
2020年 9月 YKK AP中国投資社 副総経理
2021年 4月 YKK AP中国社 副総経理
2023年 10月 YKK AP株式会社 エクステリア本部 副本部長
2024年 4月 YKK AP株式会社 執行役員 エクステリア本部長
2025年 4月 YKK AP株式会社 常務執行役員 エクステリア本部長
エクステリア大手メーカー「YKK AP」とは
YKKはファスナー業界で圧倒的なトップブランド

画像提供:YKK AP
YKKグループはファスニング事業と建材のAP事業を中核とするグループ会社。
苅谷氏
—ですが実際、そうおっしゃる方は少なくないかもしれません。
ファスナー事業では世界のトップブランドで窓のCMに至っての認知度は高く宣伝させていただいているため、そうしたイメージが定着しているのも無理もないかと思います。
ファスナー世界市場の「巨人」 YKKの強さの源泉 | 日本経済新聞
実は、1959年にはすでに建材事業がスタートしていたんです。
ファスナー製造のために導入した大型のアルミ押出機が余力を持っていたことをきっかけに、技術を応用して建材分野へと進出した経緯があります。
アルミ合金と成形技術を生かしてアルミ建具に参入
YKKがアルミ建具の世界に足を踏み入れた背景には、ファスナー開発で培った素材技術がありました。
中でも鍵を握ったのが「56S」と呼ばれるアルミ合金の量産化です。
当初はファスナー用の素材として開発されたものですが、その軽さと強度に着目し、応用先として建材が挙がりました。
そこからアルミサッシやドアといった住宅建材の製造が本格化し、「YKK AP」というブランドが誕生。
APとは、Architectural Productsの頭文字をとったもので、「建築用工業製品を提供する会社」と言うことになります。
単なる素材メーカーではなく、住まいに関わる高性能な製品を手がける存在へと進化を遂げました。
世界で認められている確かな品質のモノづくり
苅谷氏
YKKファスニング事業のモノづくりが世界で高く評価されている理由の一つに、一貫生産体制があり、ファスナーそのものだけでなく、その製造機械まで自社で開発しているのです。
高品質な製品を低コストで安定的に生み出す仕組みが、自社の中に完結している。
これほどまでに製造工程を極めているメーカーは、そう多くありません。
その精神は、YKK APの住宅建材・エクステリア製品にも息づいています。
現場で使われる製品だからこそ、確かな性能と長期的な信頼性が求められる。
だからYKK APは、世界中の現場でも選ばれています。
変わる暮らしに応えるYKK APのモノづくり

コロナ禍で求められた「囲む外構」への回帰
苅谷氏
—苅谷氏はそう語ります。
これまでの主流は“オープン外構”でしたがトレンドが変わりつつあることを感じています。
コロナ渦では在宅時間が長くなったことで、人々の意識はプライバシーや安心感へと向かいました。
そこで高まったのが“囲む外構”へのニーズ。しっかり閉じるのではなく、ゆるやかに仕切る。その絶妙なバランスが、今の暮らしにちょうどいいと支持されています。
実際、北海道などの土地が比較的とりやすい地域でもプライベート空間を仕切るトレンドが生まれてきつつあります。
10年後、20年後に気づく“いい買い物”だったと思える理由
ネジ1本から網戸のネットまで“自社で生産”=一貫生産体制
苅谷氏
周辺のモノづくりの生産技術だけでなく、それに関わる設備まで含めた一貫生産。という意味です。」
YKK APが掲げる“ものづくりの原点”ともいえるのが、自社完結の一貫生産体制です。
アルミの鋳造から金型設計、そして部品製造まで社内で手がけているからこそ、古い製品でも補修用の部品を安定的に供給することができます。
過去の商品でも対応できるような、開発・製造・供給体制になっているため、部品が手に入らないから全部交換しなきゃいけない。
そのようなことを避けやすくなります。
たとえ10年以上前の製品であっても、「直せる・使い続けられる」選択肢を残せることが一貫生産体制のメリットです。
一見目立たないこだわりかもしれませんが、長く暮らす住まいにおいて、これほど心強い“安心”はないと思います。
職人不足にも配慮した“高品質な簡単施工”
苅谷氏
でも実際は、逆なんです。」
苅谷氏
「世の中では、商品を施工した後、雨漏りだったり、施工ミスがあったりするお困りのお客さん、すごく多いんですね。
省施工っていうのは一般のお客さんになかなか良さが伝わらないんですけど、私たちは、省施工の先は品質です。というふうにお伝えさせていただいております。」
設計段階から“短工期・高品質”を実現する構造にこだわる理由は、まさに現場のリアルに向き合ってきたからこそです。
近年は特に、左官職人をはじめとした施工技術者の不足が深刻です。
YKK APは、部材の接合方法や組み立て工程を簡素化しながらも、雨漏りや施工ミスを防げる“構造で守る品質”を追求しています。
結果として、プロの作業効率を高めるだけでなく、技術だけに頼らない確実な施工ができることによって施主側にとっても安心して住み続けられる仕上がりを実現しています。
独自の商品検証
苅谷氏
YKK APが行う性能試験は、単なるカタログスペックの確認ではありません。
JIS規格に基づく評価だけでなく、“生活者基準”という独自の高いハードルを設け、現実の暮らしで起こりうる厳しい条件下での検証を行っています。
たとえば砂嵐がどれだけ部材に影響を与えるか、あるいは強風と豪雨が同時に吹きつけた場合、製品はどう反応するのか。こうした実験を通じて見えてくる課題が、製品の改良や新たな価値につながっていきます。
「リアルな暮らしに耐えられるものを、リアルな条件で試す」それが、YKK APの品質づくりの根幹です。
まとめ

YKK APのモノづくりは、ただ機能やスペックを追い求めるのではなく、「10年後、20年後に“この製品を選んで良かった”と思っていただけるか」を重視してモノづくりをしていることが実感できました。
次回は、今回ご紹介しきれなかった具体的な製品群、スマートコントロールキー対応の電気錠付き門扉、リニューアルされた宅配ボックス、多彩なコーディネートが魅力のルシアスシリーズを取り上げながら、それぞれの「暮らしへの価値」をさらに深掘りしていきます。